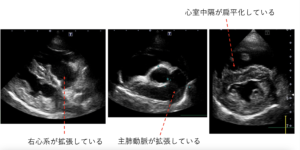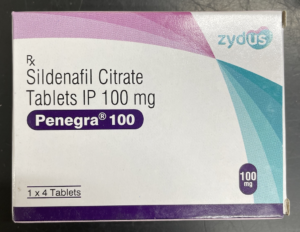当院では、狂犬病の予防接種を4月から順次行っております。札幌市から届いた封筒をご持参の上、お越しください。注射後のアレルギーに備えて、平日の午前中に接種することをお勧めしております。
接種についてご不明な点や心配な点がございましたら、お気軽にスタッフにお伝えください。
ワンちゃん、ネコちゃんのフィラリア予防薬も処方しております。
同時にノミ・マダニの予防ができるオールインワンタイプも大変人気です。
ワンちゃんには錠剤タイプとおやつタイプがお選び頂けます。
ネコちゃんには背中につける液体タイプがございますので、飲み薬が苦手な子にも安心です。
フィラリアの予防期間は5月頃〜10月頃。ノミ・マダニは春〜秋に活発になります。まずはご相談ください。
今シーズンもすでにたくさんの方が予防薬を取りにきてくださり、入荷に時間がかかるお薬も出てきております。在庫がない場合もございますので、"前もってお電話"頂けますとお待たせすることが少なくなるかと思います。